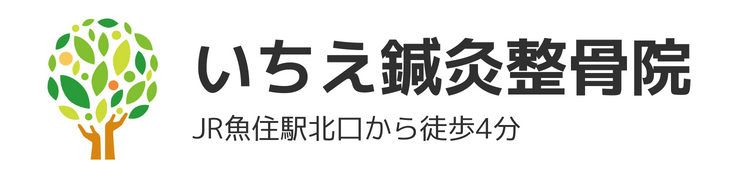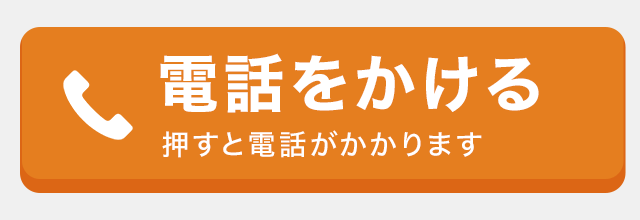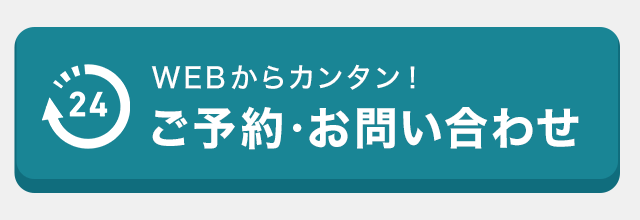肩が上がらない…五十肩の症状・原因・解消法を徹底解説!

五十肩

五十肩(ごじゅうかた)は、中高年に多く見られる肩の痛みや可動域の制限を伴う症状の総称です。
正式には「肩関節周囲炎」と呼ばれ、特に40~60代の方に多く発症するため「四十肩」「五十肩」と呼ばれることもあります。
日常生活に支障をきたすことがあり、放置すると症状が長引くため、適切なケアと治療が重要です。
本記事では、五十肩の原因、症状、治療法について詳しく解説していきます。
五十肩の原因とは?
五十肩の原因は完全には解明されていませんが、加齢による肩関節周囲の組織の劣化が主な要因とされています。具体的には、以下のような原因が考えられます。
-
肩関節の炎症
肩の関節包(かんせつほう)と呼ばれる部分に炎症が起こることで、痛みや可動域の制限が生じます。これが五十肩の典型的な症状です。 -
腱板の変性
肩の動きを支える腱板(けんばん)が加齢により弱くなり、損傷しやすくなることで、炎症や痛みが発生します。 -
血流の低下
年齢とともに血流が低下し、組織の修復力が落ちることで、炎症が慢性化しやすくなります。 -
長期間の不適切な姿勢
デスクワークやスマートフォンの使用が増えることで、肩や首周りの筋肉が硬直し、肩関節に負担がかかることも原因の一つです。
五十肩の症状
五十肩の症状は、主に以下の3つの段階に分けられます。
-
炎症期(急性期)
・肩を動かすと鋭い痛みが走る
・夜間痛があり、寝ているときに痛みで目が覚めることがある
・動かさなくても痛みを感じる -
拘縮期(慢性期)
・痛みは軽減するが、肩の動きが大きく制限される
・「腕を上げる」「背中に手を回す」などの動作が困難になる -
回復期
・徐々に痛みが消え、可動域が改善される
・通常、発症から1~2年で回復することが多い
いちえ鍼灸整骨院での治療方法
五十肩の治療には、病院でのリハビリや薬物療法もありますが、いちえ鍼灸整骨院ではより自然な方法で痛みを和らげ、可動域を改善することが可能です。
1. 鍼灸治療
鍼(はり)を使用することで、筋肉の緊張を和らげ、血流を促進します。特に「肩井(けんせい)」や「曲池(きょくち)」などのツボを刺激することで、痛みを和らげる効果が期待できます。
2. 手技療法(マッサージ)
硬くなった筋肉をほぐし、血流を改善することで、肩の可動域を広げます。特に肩甲骨周りの筋肉を緩めることで、肩関節への負担を軽減できます。
3. ストレッチ・運動療法
無理のない範囲でストレッチやリハビリ運動を行うことで、可動域を回復させます。例えば、ゆっくりと腕を前後に振る「振り子運動」や、壁を使って腕をゆっくり上げる「壁這いストレッチ」などが効果的です。
4. 温熱療法
温熱パックやお灸を使って患部を温めることで、血流を促進し、痛みを緩和します。特に寒い季節や冷え性の方に効果的です。
自宅でできるケア
五十肩の改善には、自宅でのケアも重要です。以下のポイントを意識して、日常生活に取り入れてみましょう。
-
温める
入浴時に肩をしっかり温めたり、ホットタオルを使ったりすることで血流を改善できます。 -
無理のないストレッチ
痛みのない範囲でゆっくりと肩を動かすことで、関節の可動域を維持できます。 -
姿勢を正す
猫背にならないように意識し、デスクワークの際には定期的に肩を回したり、背筋を伸ばしたりすることが大切です。
まとめ
五十肩は放置すると長引きやすい症状ですが、適切なケアと治療によって早期回復が可能です。
鍼灸や整骨院での施術を取り入れることで、痛みの軽減や可動域の改善が期待できます。
もし肩の痛みを感じたら、無理せず専門家に相談し、早めに対策を始めましょう。